運転免許試験講座
6月に続いて、今週もサーバーに繋がりにくい状況が頻発しておりました。
お盆休みで担当者が不在で復旧まで大変時間が掛かかりご迷惑をお掛けしました。
契約しているサーバー会社のサービスが今年10月に停止することとなり、現在少しずつ別のサーバー会社に移行する作業をしております。
移行作業期間中に不安定な状態が続くことがあり、ご利用の方々にご不便・ご迷惑をお掛けしており大変申し訳ございません。
なお、これを機に12年間使っている現在の第3世代のシステムの刷新作業もしております。
この12年間でWEB周辺の技術も大変進化しまして、かなり古くなってしまっている状態です。
AIを取り入れた学習サービス(引き続き無料が基本です)を今年中にリリースする予定です。なお、現行のシステムは3年後(2028年夏)に廃止する予定です。
詳細は、10月頃にアナウンスさせて頂きます。また、合わせてYouTubeによる動画解説も公開予定です。
220. tyrogon さん
[コメント]
これは標識じゃなくて標示ですよね
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
413
[問題文]
下図の標示のある場所では、停車が禁止されている。
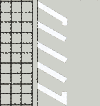
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
この道路標示は、「斜め駐車」の標識です。
駐車する場合は、白線に従って斜めに駐車してくださいね、という意味です。
○と答えた方は、下図の標識と勘違いしています。
区別して覚えてくださいね。

変更反映日時: 11年06月18日
219. takeshi1 さん
[コメント]
「避難」を見落としていました
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
168
[問題文]
運転中に大地震が発生したときは、安全な場所へ車で避難する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
大地震が発生したときは緊急自動車の交通を確保して混乱を防ぐために、車を使っての避難はしてはいけません。
早く逃げたいという気持ちはよーく分かりますけど。。。
変更反映日時: 11年06月18日
218. rbev93x さん
[コメント]
750kg以上がけん引免許必要。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
426
[問題文]
車両の総重量が750キログラムの被けん引車をけん引する場合には、けん引する自動車の免許とは別にけん引免許が必要になる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
被けん引車(けん引される側の車のこと)の車体総重量が750キログラムならOKです。
問題は、750キログラムを超えた場合です。
少し、細かいですかね?!
で、けん引免許とけん引される車の総重量との関係を確認しておきましょう。
1. 車両総重量が750キログラム以下 → けん引免許は不要
2. 車両総重量が750キログラムを超える → けん引免許が必要
3. 車両総重量が2,000キログラム未満 → 小型トレーラー限定けん引免許でも運転可能
変更反映日時: 11年06月18日
217. rbev93x さん
[コメント]
いわゆる小型特殊自動車ですね。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
129
[問題文]
車とは、自動車及び原動機付自転車のことである。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
車には、自動車、原動機付自転車の他に軽車両も含まれます。
軽車両というのは、自転車や荷車などのことです。
変更反映日時: 11年06月18日
216. rbev93x さん
[コメント]
左折ならやむをえないかと。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
274
[問題文]
交差点を左折する場合でも、路線バス以外の自動車は路線バス専用通行帯を通行することはできない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
「路線バス専用通行帯」は、路線バス以外は原則として通行できません。
ただし、原則には例外があって、以下のような場合には通行が許されています。
1. 交差点で右左折する場合
2. 前方が工事中の場合
3. 緊急自動車に道を譲る場合
変更反映日時: 11年06月18日
215. rbev93x さん
[コメント]
基本的に、左側走行です。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
543
[問題文]
追越しややむを得ない場合を除いて、二つの車両通行帯にまたがって通行してはいけない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
通常は、決められた車両通行帯の枠内で運転するようにしましょうね。
変更反映日時: 11年06月18日
214. rbev93x さん
[コメント]
「駐車した」という所がよくない。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
38
[問題文]
下図の標識のある場所で、休憩のため車を駐車した。

[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
これは「停車可」の標識で、残念ながら駐車はできません。
「停」車ができるのみです。
ちなみに、下図が「駐車可」の標識です。
では、問題!
この標識がある所は、どういう所でしょう?
わざわざ「停車可」と言っているのですから、普段は停車が禁止されている所に設置されています。
比較的長い駐停車禁止区間で、ココだけでは停車しても大丈夫だよ、という感じで設置されていることが多いですね。
<font color="#CC0000">停車の「停」と、駐車(parking・パーキング)の「P」としっかり区別して覚えてくださいネ。</font>
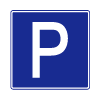
変更反映日時: 11年06月18日
213. yunncyanman さん
[コメント]
確か80Kmだった気がします。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
311
[問題文]
高速自動車国道で登坂車線を走行する場合には、最低速度に達しない速度で運転してもかまわない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
最低速度の規制を受けるのは、「本線車道」です。
登坂車線は、「本線車道」ではありませんから、最低速度を守る必要はありません。
むしろ、こう配がきつくて速度が出せない車が通るのが登坂車線ですから当たり前と言えば当たり前ですよね。
このほかにも、本線車道ではない減速車線や加速車線、路側帯などもモチロンそうです。
ところで、受験者の心理なのかもしれませんが、以前この問題文の最後を「運転してもかまわない」ではなく「運転することができる」と表現を変えてみたところ、正解率がグーんと高くなりました。
この問題文ではどちらも意味は同じなのですが、「してもかまわない」って表現すると、何かマズイんじゃないかなぁと思う人が多くなるんだろうと思います。
試験では引っ掛けが出ますから、イメージで答えると出題者の思惑にはまってしまいます。問題文の表現に惑わされず冷静に問題文に書かれていることを分析してみて下さい。
変更反映日時: 11年06月18日
212. shige6448 さん
[コメント]
山と崖ってのがわかりにくい。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
19
[問題文]
片側が崖になっている道路で対向車と行き違う場合には、山側の車線の車が停止して道を譲るようにする。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
山側ではなく崖側の車が停止して道を譲ります。
どうしてでしょうか、分かりますか?
<font color="#CC0000">対向車との行き違いに気を取られてハンドル操作を誤った場合に、崖側の車は転落する恐れがあるからです。
一方、山側の車が操作を誤ったとしても、車の側面を山に擦る程度で済みますから。</font>
[ユーザー様投稿解説]
Q. 崖側の車が登りの場合でも、山側の下りの車に路を譲る事になるのでしょうか?
A. 解説にかいてある通り、崖と対向車の両方を気にしながら運転するのは、とても大変です。
万が一転落、なんてなったらもう…。
山側の対向車に先に行ってもらって、あとから広くあいた道を安心して運転するほうが、安全です。
A. 私も、教習所では「常に危険な側が安全確保のために対向車に道を譲ること」と教わりました。
道を譲る=安全確保のためと覚えると、分かりやすいと思います。
A. 短く「安全な方が先に行く!」って覚えようと思います。右左折直進も、比較的安全な方が先に行くので、それと一緒に覚えまーす。
変更反映日時: 11年06月18日
211. nugget さん
[コメント]
学科試験でもこんなことあるのかな?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
213
[問題文]
30km/hで進行しています。どのようなことに注意して運転しますか?
前方に車が停車しているので、そのままの速度で右側へ進路を変更して側面を通過する。

[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
そのままの速度で進路変更すると、対向車の車と正面衝突していまいますよ。
ちなみに、この道路の中央線が黄色ですね。中央線が黄色って何でしたっけ?
そう、右側部分へのはみ出し禁止です。
ですから、通常は右側にはみ出して通行はできないのですが、前の車は止まっている(進行中ではない)ため「追越し」には該当しません。
ちょうど、「障害物」があるのと同じ扱いです。
ですから、この場合は反対車線(右側部分)の交通に注意しつつ、反対車線へのはみ出しを最小限にして横を通り過ぎて下さい。
でないと、この車がどかない限り後の車は前に進めなくなってしまうので。
★「危険予測問題」へのアプローチ
危険予測では、「そのままの速度で」という表現が非常に!よく使われます。
この表現が出てきたら99%その選択肢は×です。危険を予測する問題で「そのままの速度」というのは不適切です。もう少し安全に対する謙虚な態度が必要です。
変更反映日時: 11年06月18日
![[全免許] (普通・原付・二輪)運転免許学科試験・無料問題集・計画を立てる](http://www14.resource-database.com/img/menu/plan.gif)
![[全免許] (普通・原付・二輪)運転免許学科試験・無料問題集・問題を解く](http://www14.resource-database.com/img/menu/output.gif)
![[全免許] (普通・原付・二輪)運転免許学科試験・無料問題集・理解を深める](http://www14.resource-database.com/img/menu/input.gif)
![[全免許] (普通・原付・二輪)運転免許学科試験・無料問題集・分析する](http://www14.resource-database.com/img/menu/analyze.gif)
![[全免許] (普通・原付・二輪)運転免許学科試験・無料問題集・仲間と交流する](http://www14.resource-database.com/img/menu/communicate.gif)
![[全免許] (普通・原付・二輪)運転免許学科試験・無料問題集・資料館](http://www14.resource-database.com/img/menu/information.gif)
![[全免許] (普通・原付・二輪)運転免許学科試験・無料問題集・参加する](http://www14.resource-database.com/img/menu/join.gif)